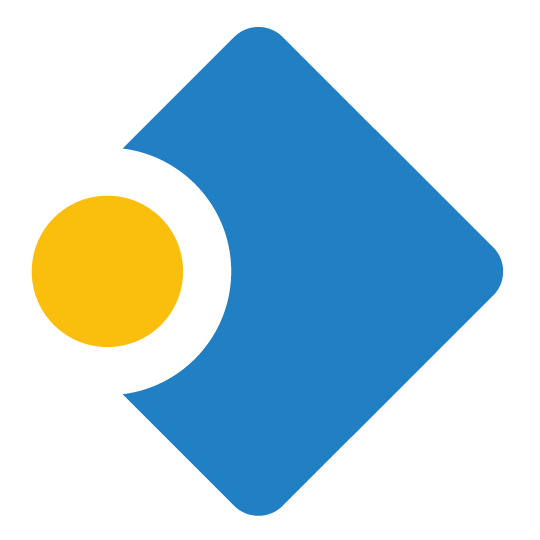電子処方箋について
電子処方箋は、オンライン資格確認の仕組み(オンライン資格確認等システム)を基盤とした「電子処方箋管理サービス」を通して、医師、歯科医師、薬剤師間で処方箋をやり取りする仕組みです
医師・歯科医師が処方箋を「電子処方箋管理サービス」に送信し、薬剤師がその処方箋を薬局のシステムに取り込み、お薬を調剤します
お薬を調剤した後、薬局は調剤結果を「電子処方箋管理サービス」に送信します
調剤結果は重複投薬や併用禁忌がないかのチェックなどに活用されます
病院・診療所でできるようになること
処方箋の事前送付が行えるようになるほか、丁寧な患者対応への注力や、医療機関・薬局間の円滑なコミュニケーション、より効果のある重複投薬等の抑制を行えるようになります
重要なお知らせ
令和7年9月29日に開催された「第5回電子処方箋推進会議」において、以下のとおり新たな電子処方箋補助金の取扱いが示されました
○令和7年10月以降の医療情報化支援基金(ICT基金)による電子処方箋の導入補助について、補助対象とする導入期限を令和8年9月まで延長した上で、令和7年10月以降に導入した施設に対しても補助を実施する
また、補助対象の機能について、従来の院外処方機能に加えて院内処方機能も補助対象に追加※する
○令和8年10月以降の補助の取扱いについては、令和8年夏までにとりまとめられる電子カルテ/共有サービスの普及計画を踏まえて、電子処方箋と電子カルテ/共有サービスが一体的に導入が進むよう、改めて補助の取扱いを検討する
※院内処方情報の電子処方箋管理サービスへ登録する際に、電子署名は求めていないため、電子署名に必要となるHPKIカードの保有等は必ずしも必要ない
補助事業においても電子署名を必要としない施設は、HPKIカードの保有等は求めない
~電子処方箋の仕組みやメリットについての資料~
~電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き~
~電子処方箋における電子署名について~
※マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォン(NFC対応端末)について
↑マイナ資格確認アプリを利用するには、NFC対応かつ拡張Lc/Le(拡張APDU)に
対応している必要があります。iPhoneは単体でご利用可能です。
※HPKIカードの動作が確認されているICカードリーダについて
医療機関等向け総合ポータルサイト
医療機関等向け総合ポータルサイトの電子処方箋管理サービスのページになります
登録等の流れについて
1.HPKIカード申し込み
※HPKIカードではなくマイナンバーカードを利用した電子署名の申請について
※マイナポータル上でのマイナンバーカードを活用した電子署名の申請について
※「HPKI セカンド電子証明書」とスマートフォンの紐づけ手順について
2.電子署名を行うための準備(HPKIカードの発行申請 等)完了の登録
導入依頼
3.電子処方箋の利用申請
導入
4.電子処方箋の運用開始日入力
電子処方箋に関するよくある質問について
医療機関向け総合ポータルサイトのリンクです
令和7年4月以降の点数及び届出について
<令和7年4月以降の医療DX推進体制整備加算の取扱いについて>
・電子処方箋の体制を導入しなくてもよい点数として、加算4、5、6が新設された
・加算6の点数(電子処方箋の体制を導入せず、マイナ保険証利用率が最も低い場合の点数)は8点とされ、現在の加算3の8点と同じ点数を4月以降も引き続き算定することが可能
・マイナ保険証利用率の実績要件は、昨年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したこと等を踏まえて引き上げられるが、利用率が上がれば、より高い点数を算定できる
令和7年4月からは、電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有している場合の点数である「加算1、2、3」と、電子処方箋要件がない「加算4、5、6」に分かれることとなります
また、令和7年3月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が同年4月以降に「加算1、2、3」を算定する場合、同年4月4日までに新たな様式による届出直しが必要となります。なお、「加算4、5、6」を算定する場合は新たな様式による届出直しは不要です
令和7年9月以降は下記の表の点数、利用率になります
| 電子処方箋体制の要件 | 加算 | 点数 | 9月30日 まで | 2025年10月1日 ~2026年2月28日 | 2026年3月1日 ~5月31日 |
| あり | 加算1 | 11点 | 45% | 60% | 70% |
| 加算2 | 10点 | 30% | 40% | 50% | |
| 加算3 | 8点 | 15% | 25% | 30% | |
| なし | 加算4 | 9点 | 45% | 60% | 70% |
| 加算5 | 8点 | 30% | 40% | 50% | |
| 加算6 | 6点 | 15% | 25% | 30% |
※電子カルテ情報共有サービスについて
当該加算の施設基準である「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること」について、2025年9月30日までの経過措置が設けられていましたが、電子カルテ情報共有サービスの「医療法等の一部を改正する法律案」が未成立であることから、2026年5月31日までに延長されました